空家管理サービス 2025.03.27
空家対策措置法とは?相続した空き家を“特定空家”にしないためのポイントと対策
日本空き家サポーターとして、今後の空き家問題について
今なぜ空き家対策に国が動き出しているのか(少々長くなりますが・・・!)、
まとめてみました。相続により空き家になってしまったご実家の管理、転勤になってしまったので数年の管理など、様々な事情に寄り添えるよう小川工務店からも情報を発信させていただこうと思っています。
日本全国で増加する空家は、地域社会や経済にさまざまな影響を及ぼしています。この問題に対応するために制定されたのが「空家対策措置法」です。今回は、この法律の基本的な概要と目的を解説し、特定空家に指定されるリスクやその対応策、さらに2023年の法改正による最新情報について詳しく紹介します!
空家対策措置法とは?
相続した空き家を“特定空家”に
しないためのポイントと対策

【目次】
空家対策措置法とは?基本的な概要と目的
空家対策措置法、正式名称「空家等対策の推進に関する特別措置法」は、2015年に施行され、日本全国で増加する空き家問題に対応するために作られた法律です。この法律の目的は、放置されている空き家がもたらす安全性や景観の問題を解決し、地域社会の健全な発展を促進することにあります。特に、老朽化した空き家が倒壊の危険を伴う場合や、不審者の侵入による犯罪の温床となるリスクを未然に防ぐことを重視しています。
この法律は以下のような目的を持っています:
- 安全性の確保:倒壊や火災、犯罪などの危険を防ぐため。
- 景観の維持:地域の美しさを保つために。
- 資産管理の促進:空き家の所有者に対して、適切な管理を促す。
- 社会コストの削減:行政による強制的な解体や清掃にかかる費用を減らす。
空家対策措置法の施行後、各自治体には空き家の現状を調査する権限が与えられ、特に管理が不十分な空き家に対しては「特定空家」という指定が行われるようになりました。この指定を受けると、所有者には行政からの指導や罰則、場合によっては解体命令が下されることもあります。このように、空家対策措置法は地域社会の安全と秩序を守るための重要な役割を果たしているのです。
特定空家とは何か?その基準と影響
特定空家とは、簡単に言うと、管理が不十分で放置されている空き家の中でも、特に周囲の安全や地域環境に悪影響を及ぼすと判断されたものを指します。この指定は、市区町村の調査と判断によって下され、指定基準は法律で明確に規定されています。
特定空家とされる基準
- 倒壊または著しい保安上の危険がある:建物が著しく老朽化し、倒壊のリスクが高い場合。
- 衛生上有害である:ごみの放置や害虫の発生など、公共衛生に悪影響を及ぼす場合。
- 景観を著しく損なう:建物が破損し、地域の美観を損ねている場合。
- 適切な管理が行われていない:所有者が管理を怠り、不法侵入や火災のリスクが高い場合。
これらの基準に基づき「特定空家」に指定されると、所有者にとっては様々な影響が及びます。例えば、行政からの指導に従わない場合、強制的な解体や修繕が行われ、その費用が所有者に請求されることがあります。また、特定空家に指定されると土地の固定資産税の減額措置が解除されるため、税負担が大幅に増加するリスクも存在します。
特定空家の指定がもたらす影響
- 行政の介入:指導、命令、場合によっては代執行(強制解体)。
- 費用の発生:修繕や解体費用が自己負担となる。
- 税負担の増加:固定資産税の優遇措置が解除され、税額が通常の6倍になるケースも。
特定空家に指定されることは、所有者にとって経済的・心理的に大きな負担となります。そのため、空き家の適切な管理がいかに重要であるかが分かりますね。
空家対策措置法が与える税金の影響
空家対策措置法は、空き家の所有者に対して大きな影響を与える法律ですが、その中でも特に注目すべきは税金への影響です。空き家の管理状況が悪く「特定空家」に指定されると、土地の固定資産税に関する優遇措置が解除されるため、税負担が大幅に増加します。
固定資産税の優遇措置とは?
通常、住宅用地として使用されている土地には固定資産税の軽減措置が適用されます。具体的には、以下のような優遇が受けられます:
- 200㎡以下の部分:税額が1/6に軽減。
- 200㎡を超える部分:税額が1/3に軽減。
しかし、「特定空家」に指定されると、この軽減措置が解除され、税率が通常の課税水準に戻されます。これにより、税額が6倍に跳ね上がるケースも珍しくありません。
他の税負担への影響
加えて、空き家を長期間放置することで以下のようなリスクも発生します:
- 都市計画税:固定資産税と同様、軽減措置が解除される可能性。
- 解体費用:行政代執行による解体が行われた場合、その費用が全額自己負担。
税金負担を軽減するための対策
税負担を軽減するためには、以下のような対応が求められます:
- 適切な管理:定期的に清掃や修繕を行い、特定空家に指定されないようにする。
- 売却または活用:空き家を売却するか、賃貸やリフォームを通じて有効活用する。
- 専門家への相談:税理士や不動産業者に相談し、最適な対策を講じる。
空家対策措置法は、空き家問題の解消を目指すための法律ですが、所有者にとっては大きな負担となり得ます。そのため、法律の内容を正しく理解し、早めの対応を心がけることが重要です。
特定空家に指定されるリスクを知ろう
特定空家に指定されることは、空き家所有者にとって深刻なリスクを伴います。この指定は、放置された空き家が周囲の安全や環境に問題を引き起こす場合に行われますが、指定を受けることで発生する問題は多岐にわたります。具体的にどのようなリスクがあるのか、詳しく見ていきましょう。
特定空家に指定されることで発生するリスク
- 税額の増加:固定資産税の優遇措置が解除され、税金が大幅に増加。
- 行政指導・命令:改善命令が出され、応じない場合は強制的な措置が取られる可能性。
- 解体費用の負担:行政代執行による解体が行われた場合、その費用が所有者に請求される。
- 資産価値の低下:特定空家に指定されると、不動産としての価値が大幅に下がる。
- 地域への悪影響:周囲の住民とのトラブルや、地域全体の評価低下に繋がる。
リスクを回避するためのポイント
- 空き家の現状把握:定期的に建物や土地の状態を確認。
- 早期の修繕:老朽化が進む前に修繕を行う。
- 適切な管理計画の策定:長期的な視点で管理方法を考える。
- 自治体との連携:地域の空家対策支援制度を活用する。
特定空家に指定されるリスクは、所有者だけでなく、地域社会全体に影響を及ぼす可能性があります。そのため、空き家を放置せず、早めに対策を講じることが大切です。
固定資産税が6倍に?特定空家が引き起こす税負担
特定空家に指定された場合、最も大きな経済的影響を受けるのが固定資産税です。通常、住宅用地には軽減措置が適用されており、税額が大幅に抑えられています。しかし、特定空家に指定されるとこの優遇措置が解除され、税額が6倍になることもあります。
具体的な税負担の変化
- 軽減措置の解除:住宅用地に適用されていた1/6または1/3の軽減措置が適用外となる。
- 通常税率の適用:これにより、税額が大幅に増加。
- 例:従来の固定資産税が10万円だった場合、特定空家指定後には60万円になる可能性も。
税負担を軽減するための具体策
- 空き家の活用:賃貸や売却を通じて、特定空家に指定されるリスクを回避。
- 解体の検討:建物を解体し、更地にすることで税負担を抑える。
- 専門家への相談:不動産業者や税理士に相談し、最適な対応策を立てる。
税負担の影響が及ぶ他の面
- 地域経済への影響:空き家が増えることで、地域全体の経済活動が停滞。
- 家庭の予算圧迫:特定空家に指定されると、突然の高額な税負担が家計を圧迫する。
特定空家が引き起こす税負担は、所有者にとって非常に大きな問題です。そのため、放置せず早めの対策を講じることが重要です。特に、法律や税制度の変更に敏感に対応し、適切な管理を行うことでリスクを最小限に抑える努力が求められます。
管理不全空家との違いと注意点
空家対策措置法では、「特定空家」と「管理不全空家」がよく取り上げられますが、これら二つの違いを理解することは非常に重要です。これらの違いを知ることで、空き家の管理方法や対応策を適切に選ぶことができます。
管理不全空家とは?
管理不全空家は、まだ特定空家に指定されるほどではないものの、適切な管理が行われておらず、周囲に影響を及ぼし始めている空き家を指します。例えば、以下のような状態が該当する場合があります。
- 雑草の繁茂やゴミの放置による軽度の景観悪化。
- 軽微な建物の損壊(例:屋根や窓の一部が破損している)。
- 周囲への危険性は低いが、放置することで今後問題が拡大する可能性がある。
特定空家との違い
特定空家は、管理不全空家よりもさらに深刻な状態にある空き家で、周囲に重大な影響を及ぼしていると判断されるものです。具体的には、倒壊の危険性が高かったり、衛生面で害を及ぼす状態が挙げられます。管理不全空家が改善されない場合、最終的に特定空家に指定されるリスクがあります。
注意点と対策
- 早期対応が重要:管理不全空家の段階で適切な対策を講じることで、特定空家への指定を防ぐことが可能です。
- 定期的な点検:建物の状況を定期的に確認し、異常があれば早めに修繕を行う。
- 自治体との連携:地域の空家対策制度を活用し、助成金や専門家のアドバイスを受ける。
管理不全空家の段階で適切に対応することで、特定空家になるリスクを避けることができます。所有者としての責任を果たし、空き家が地域社会に与える影響を最小限に抑える努力が求められます。
特定空家に指定されないための対策
特定空家に指定されることを防ぐためには、空き家を適切に管理し、問題が深刻化する前に対応することが重要です。以下では、具体的な対策をいくつかご紹介します。
- 定期的な点検とメンテナンス
空き家を放置せず、定期的に建物の状況を確認しましょう。特に、以下の点に注意してください:
- 屋根や外壁の状態
- 窓やドアの破損
- 雑草の繁茂やゴミの放置
適切なメンテナンスを行うことで、特定空家に指定されるリスクを大幅に減らすことができます。
- 活用方法を検討する
空き家の活用方法を検討することも重要です。例えば:
- 賃貸物件として貸し出す。
- リフォームして売却する。
- 短期間の宿泊施設として活用する。
これらの方法により、空き家を有効活用し、管理の手間を軽減することができます。
- 専門家に相談する
空き家の管理や活用に悩んだ際は、不動産業者や税理士、建築士などの専門家に相談するのがおすすめです。また、自治体の空家対策窓口では、助成金や相談サービスを提供している場合があります。これを利用することで、具体的な対策を講じやすくなります。
- 解体を検討する
どうしても活用が難しい場合は、建物を解体して更地にするのも一つの方法です。解体には費用がかかりますが、長期的な税負担や管理コストを削減することができます。
特定空家に指定されると、所有者にとって大きな負担が生じます。そのため、事前にしっかりと対策を講じることが必要です。これらの方法を実践し、空き家を安全かつ適切に管理しましょう。
適切な管理でリスクを回避する方法
空き家を適切に管理することで、特定空家に指定されるリスクを効果的に回避することができます。管理の基本的なポイントを以下にまとめました。
空き家管理の基本ポイント
- 定期的な巡回:建物や敷地を定期的に確認し、異常がないかチェックする。
- 清掃と除草:敷地内のゴミや雑草を取り除き、衛生的な環境を保つ。
- 修繕の実施:屋根や外壁、窓などに損傷が見られた場合は、早めに修繕する。
プロに任せる選択肢
空き家の管理が難しい場合は、専門の空き家管理サービスを利用するのも良い方法です。これにより、以下のようなメリットが得られます:
- 定期的な巡回と報告
- 清掃や修繕の手配
- 緊急時の対応
管理のルールを決める
家族で空き家を所有している場合、管理の責任を明確にすることが大切です。例えば、以下のようなルールを決めると良いでしょう:
- 管理担当者を決める
- 定期的に管理状況を共有する
- 必要な費用を家族で分担する
空き家の適切な管理は、所有者にとっての義務であり、周囲の住民や地域社会への配慮でもあります。これらのポイントを実践することで、特定空家になるリスクを回避し、安全で快適な環境を維持しましょう。
空家解体にかかる費用とそのメリット
空き家を解体することは、特定空家に指定されるリスクを回避する有効な方法の一つです。しかし、解体には一定の費用がかかるため、そのメリットとコストをしっかりと理解することが重要です。
解体にかかる費用の目安
解体費用は建物の規模や立地条件によって異なりますが、以下は一般的な費用の例です:
- 木造住宅:坪単価3~5万円程度
- 鉄骨造住宅:坪単価5~8万円程度
- RC造住宅(鉄筋コンクリート造):坪単価8~12万円程度
例えば、30坪の木造住宅を解体する場合、費用は約90万円~150万円が目安となります。
解体のメリット
- 税負担の軽減:特定空家に指定されると固定資産税が増加しますが、更地にすることでそのリスクを回避。
- 土地の有効活用:解体後の土地を売却したり、新たな建物を建てることで、有効活用が可能。
- 安全性の向上:老朽化した建物がなくなることで、倒壊や火災のリスクを減少。
解体費用を抑える方法
- 自治体の助成金を活用:自治体によっては、空き家解体に対する助成金制度を設けている場合があります。
- 複数業者から見積りを取る:解体業者によって料金が異なるため、複数の業者に見積りを依頼しましょう。
- リサイクル可能な資材の売却:解体時に出る廃材の中には、売却可能なものもあります。
空き家の解体は、初期費用がかかるものの、長期的には税負担や管理コストの削減につながるため、非常に有効な選択肢です。解体を検討する場合は、費用とメリットをしっかりと比較し、適切な判断を行いましょう。
法改正と今後の空家対策の展望
2025年3月時点で、空家対策措置法はさらなる改正が予定されており、空き家問題の解決に向けた取り組みが強化されています。この法改正の背景には、増加する空き家の放置問題と、それに伴う地域社会への影響が深刻化していることがあります。
法改正のポイント
- 管理不全空家の新設:これまで特定空家に該当しなかった管理不全空家に対しても、行政が指導を行う権限が強化されました。
- 自治体の権限拡大:自治体が空き家問題に迅速に対応できるよう、調査や指導、強制執行の手続きが簡略化されました。
- 助成金制度の拡充:空き家の解体やリフォームに対する助成金が充実し、所有者が対策を講じやすくなりました。
今後の空家対策の展望
- 地域社会との連携:自治体だけでなく、地域住民やNPO法人との連携が進むことで、地域全体で空き家問題に取り組む体制が整備されつつあります。
- デジタル技術の活用:空き家の状況を把握するため、ドローンやIoT技術を活用した調査や管理が普及すると予想されます。
- 空き家の有効活用促進:リフォームやコンバージョン(用途変更)を通じて、空き家を地域資源として活用する動きが加速。
所有者が取るべきアクション
- 法改正の内容を把握する:自治体の説明会や専門家のアドバイスを活用し、新しいルールに対応しましょう。
- 早期対応を心がける:建物の老朽化が進む前に、管理や活用の方針を決定する。
- 行政支援を活用する:助成金や相談窓口を積極的に利用し、負担を軽減する。
空家対策措置法の改正とともに、空き家問題の解決に向けた取り組みがさらに進むことが期待されています。所有者としても、法律や制度をきちんと理解し、積極的に対応していくことが重要です。
2023年改正の主なポイントと影響
2023年に施行された空家対策措置法の改正は、空き家問題に対処するための施策をさらに強化する内容となっています。この改正は、特定空家や管理不全空家への対応をより迅速かつ効果的に行うことを目的としています。以下に、主な改正ポイントとその影響を詳しく解説します。
主な改正ポイント
- 管理不全空家の新設
- 特定空家に至らないものの、管理状態が悪く地域に悪影響を与える空家が「管理不全空家」として新たに定義されました。
- 管理不全空家に対しても行政が指導や是正命令を出せるようになり、所有者に対する管理の責任が強化されました。
- 自治体の権限強化
- 自治体が空き家を調査し、必要に応じて指導や勧告を行う権限が拡大。
- 指導に従わない場合には、行政代執行(強制解体など)の手続きがスムーズに行えるようになりました。
- 税制面での影響
- 特定空家や管理不全空家に指定された場合、従来の固定資産税の軽減措置が解除されることで税負担が増加します。
- 空家の管理を怠ることで、税金や行政代執行の費用が増大するリスクが高まりました。
改正の影響
- 空き家所有者への影響:
- 所有者は、空き家の管理に対する責任が増し、放置することで経済的負担が増大するリスクが高まりました。
- 地域社会への影響:
- 空き家問題が迅速に解決されることで、安全性の向上や景観の改善が期待されています。
- 不動産市場への影響:
- 空き家の有効活用が促進されることで、不動産市場の活性化が見込まれています。
所有者が行うべき対策
- 空き家の現状を把握し、特定空家や管理不全空家に指定されるリスクを避ける。
- 修繕や解体を検討し、適切な管理を行う。
- 法改正に基づいた自治体の支援制度を活用する。
2023年の法改正は、空き家問題に対する取り組みをさらに強化するものです。所有者としては、法律の内容を理解し、早めの対応を心がけることが求められます。
自治体が提供する補助金や支援制度を活用
空き家の管理や解体には費用がかかるため、自治体が提供する補助金や支援制度を活用することが大切です。これらの制度は、所有者の経済的負担を軽減するとともに、空き家問題の解消を促進するために設けられています。
主な補助金や支援制度
- 解体費用の補助
- 多くの自治体では、特定空家や管理不全空家に指定される可能性がある空き家の解体費用の一部を補助しています。
- 補助金額の例:解体費用の50%(上限50万円~100万円)など。
- リフォーム助成金
- 空き家を賃貸用や居住用にリフォームする場合、その費用の一部を補助する制度です。
- 古民家再生や耐震改修に対する助成金も含まれる場合があります。
- 管理費用の補助
- 空き家の適切な管理を促すため、清掃や修繕費用を補助する制度。
- 特定の条件を満たす場合に適用されます。
- 空き家バンクの活用支援
- 空き家バンクに登録することで、売却や賃貸をスムーズに進められるよう支援。
- 登録料や手数料の補助がある自治体もあります。
※補助金に関しまして、残念ながら現在(2025年3月)時点で
柏市・松戸市・我孫子市など空き家の解体費用そのものを対象とした補助金制度は確認できませんでした。その他の関連制度として、「老朽危険なコンクリートブロック塀の撤去費用」を対象とした補助金があります。
補助金を活用するメリット
- 経済的負担の軽減:高額な解体費用やリフォーム費用を抑えることができます。
- 空き家の有効活用:補助を受けてリフォームすることで、空き家を賃貸や売却に活用しやすくなります。
- 地域社会への貢献:適切な管理や活用を行うことで、地域全体の景観や安全性が向上します。
補助金を申請する際の注意点
- 自治体ごとの条件を確認:補助金制度は自治体によって内容や条件が異なるため、事前に詳細を確認しましょう。
- 必要書類の準備:申請には、見積書や土地・建物の登記情報などが必要です。
- 申請期限を守る:期限を過ぎると補助を受けられないことがあります。
自治体が提供する補助金や支援制度を賢く活用することで、空き家の管理や解体を効率よく進めることができます。これらの制度を活用し、空き家問題を解決する第一歩を踏み出しましょう。
未来のために空家問題を考える重要性
空家問題は個人の資産管理だけでなく、地域全体の住環境や安全性にも深く関わります。特定空家に指定されるリスクや税負担の増加を避けるためには、日頃の適切な管理が欠かせません。また、2023年の法改正による新たな動きや自治体の支援制度を積極的に活用することも重要です。これらの知識を活かし、空家問題に対処することで、地域社会全体の発展に寄与しましょう。
小川工務店では、日本空き家サポートと提携しており、空き家(住宅)に関するあらゆるご要望にお応えできるよう体制を整えています。売買・賃貸・リフォームなどのご相談を始め、空き家(住宅)の総合アドバイザーとして、是非ご活用ください!
※詳しくは、空き家サポートについての詳細ページをご覧ください。

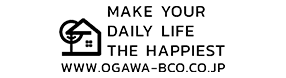
 電話をかける
電話をかける 資料請求
資料請求